※注意※
・マリかえでカンすみの百合
・太正浪漫の欠片も無い学園パロディ
・見事なまでのキャラ崩壊
・本編は広告の右下に……!(すっごく、邪魔ですね)
きっと暫く出て来られないので……今のうちに!
更新も無いのに皆さま拍手沢山ありがとうございます。
その上御礼画像もここ最近謎のエラーで表示されていなかったようで、申し訳御座いませんでした。
きっとまだまだこんなペースですが、当ブログを今年度とも宜しくお願い致します。
【拍手返信(くらゆき)】
ゆゆん様
はじめまして! 御来訪頂きありがとうございます。
かえすみの同志がいらっしゃって、私はとても嬉しいでございます。可愛いですよねちくしょう(笑)
その上拙作を『好き』だなんて仰って頂けるとは、とてもとても幸せでございます。
最近少なくて申し訳ない! でもこれからも頑張りますのでまったりお待ち下さいませ。
それでは、メッセージありがとうございました!
れぽ様(?)
アイリスちゃんね! アイリスちゃん女子高生!(笑)
きっと間違いなくランドセルになるでしょうね出るとすれば……原作でもじゅうよんさいだよ☆
キリキリさんは使えません\(^o^)/
なので是非作ってくれたまえよ……orz
蘭華様
おこんばんは~!
すっかり騙されて頂きありがとうございます(笑)
毎年やっていますが、多分当ブログが一番マトモに稼働する日だと思います。
ゲームねぇ、ゲーム……作れるスキルと創作力があれば……ッ!
取り敢えずBGM担当者捜しから始めたいと思います(逃走)
花粉は今年は喉にキました。奴らはうららかな春の最大の的でございます……。
重装備出勤が止められません(笑)
それでは、メッセージありがとうございました!
+++++++++++++++
『帝都学園 百合物語 ~ヴァレンタイン狂想曲~』
一年のうちで一番長い夜が過ぎたにも関わらず、未だ春の気配が感じられない頃。
寒さに凍え足早に歩く人混みの中、世間を知らない令嬢は友人の言葉に首を傾げた。
「どうして女であるわたくしが、バレンタインに贈り物を準備しなければなりませんの?」
場所は違えどほぼ同じ頃、花よりも団子をこよなく愛する男勝りな女子高生もまた、
彼女と同じく眉間に皺を寄せる。
「バレンタイン? 何だそれ?」
そんな相手の反応に、奇しくも彼等に全く同じ質問を投げ掛けた二人は心の中でこう呟き深い溜め息を吐く。
ああ、これは誘う相手を誤った……と。
* * *
バレンタインは男性が女性に花を贈るもの、幼い頃より欧米式の教育をされてきたすみれは、2月14日という日を疑うこと無くこう認識していた。
彼女と同じ境遇である一昔前の貴族のような上層社会の令嬢達もそれは同じらしく、何人かは婚約者から花を
貰ったと話しているのを聞いた覚えがある。
だが箱庭のような世界から飛び出した彼女が今身を置く世界では、どうやらそうではないらしい。
昨日かえでに言われなければ気にも留めなかったのだが、街の雰囲気がどこか浮かれているように感じる。
言うなればクリスマスのそれに近いだろうか。
彼女が言うには、世間のバレンタインの共通認識は、女性が好意を寄せる人にチョコレートを贈る日で
あるらしい。
驚いたすみれが目を丸くすれば何冊かの雑誌を出され、その特集記事を見れば信じざるを得ない。
いくら俗物とはいえ、世に出る女性誌全てが総じてでっち上げの記事を特集することなど無いだろう。
『何かお菓子会社の陰謀に乗るみたいで、私もあまり好きではないのだけれど……こんな機会でも無いと
言えないでしょう?』
昨日そう言って恥ずかしそうに頬を赤らめたかえでは、ボウルの中の溶かしたチョコを手際よくかき混ぜている。
作業の合間に鼻歌が聞こえるのは気分が昂っているから。
その脳裏にはきっと、彼女の想い人が浮かんでいるのだろう。
そしてその姿は、かの人物ではないすみれの目にもとても可愛らしく映る。
恋をすると女性は何倍も美しくなるとはよく聞かれるが、かえでは正にそのものなのだろう。
尤もすみれ自身が素直にそれを褒めることなどできる筈が無いのではあるが。
そんな友人の姿を暫く眺めていた彼女は、やがて深い溜息を吐くと自らの目の前にあるボウルを見つめた。
透明なそれには未だ固形のチョコレートが数枚。そして手には、かえでと同じゴム製のへら。
結局すみれは、かえでの誘いに乗りお菓子会社の陰謀に乗じることになっていたのだった。
どうしてこんなことに、などと心の中で問いかけた彼女は、目の前のボウルを電気コンロの上に置き
スイッチを入れる。
すると熱が伝わったことを告げる赤い線が、真っ黒のキャンバスに丸い模様を描いてゆく。
やがてその温度への警告を示す赤いランプが、チカチカと点滅を繰り返し始めた。
その光をぼんやりと見詰めながら、ふとすみれはこんなことを思う。
この色はいつから、かえでに誘われたあの日から憎々しい程に頭から離れない『彼女』の気配を匂わせるものに
なったのだろう、と。
赤い色が似合うわね、と少し前に言ったのはかえで。
いや、それよりも以前から身に付けていたことを考えると、元々好きな色であったのかもしれない。
そんな記憶が曖昧な頃から、すみれはこの色と、そして真っ青な空の色を見る度『彼女』のことを想うのだった。
ならばチョコレートのラッピングはこの二色を使うべきだろうか。
しかし原色であるこれらを同時に使うのは難しい。
ならばどちらかを少し軽く、しかしそれでは別の色に……
「すみれ、何してるの!!」
そこまで考えを巡らせたすみれは、突然耳に響いてきた大きな声に一瞬で我に帰る。
すると血相を変えたかえでの顔がその目に飛び込んできた。
彼女は慌ててコンロのスイッチを押して火を止めると、いつの間にか手にしていた厚手のタオルでボウルを包み、
鍋敷きの上に乗せる。よく見ればボウルの底は真っ黒に焦げ付いていた。
「こんなもの火にかけちゃ駄目じゃない! 危うく火事になるところだったわ……」
かえでは黒くなったボウルを見て溜息を吐くと、やがてそんなことを言いながらその視線をすみれの方へと移す。
見詰められた方はといえばただ呆然と、酷く焦げついたそれを見つめていた。
「あ……すみれ、そんなに落ち込まないで。ごめんなさい、私が教えていなかったのがいけなかったわ」
友人のそんな様子を気遣ってか、かえではすみれの肩に手を置きそう声を掛ける。
どうやら彼女は、普段ならばどんなことであってもすぐに反論する相手が黙ったままでいることを、
その言葉通り落ち込んだのだと捉えたらしい。
だがそんなかえでの気遣いは、一切すみれの耳に入って来てはいない。
彼女は今、それどころではないのである。
「……わたくしは」
わなわなと震える手を、すみれはぎゅっと握り締める。
そして通常よりも少しだけ長い間息を吸い込むと、ぐっとお腹の辺りに力を込めた。
「わたくしはカンナさんになんて絶っっっ対に、チョコレートを差し上げませんわよ!!」
キッチンに響いた盛大な声に驚いたのか、かえでは目を丸くする。
何がラッピングだと言うのか。何がチョコレートだと言うのか。
そもそも何故自分自身があまりにも自然に『彼女』にチョコレートを贈ることになっているのか。
思えば最初にかえでに誘われた時にも、彼女はその名前を口に出していた。
その時は確かに否定したものの、何故かすみれは今この場に参加している。
その上いつの間にか自らの思考までもが、『彼女』にチョコレートを贈ろうとしているのだ。
何故、自分が、『彼女』に!
すみれの脳裏には、この三つのキーワードがチカチカとまるでネオンのように輝いていた。
「前途多難ね、これじゃ」
肩で息をする彼女の耳に、呆れたようなかえでの声が響く。
そんな彼女の様子に再び苛立ちを覚えたすみれは、再び怒鳴り付けようと口を開いた。
だが、それは直後にその唇に触れた相手の人差し指によって制される。
その感触に一瞬だけ怯んだすみれの目に飛び込むのは、にっこりと微笑みを浮かべるかえでの顔。
「怒ってないで、一緒に作りましょう」
その上続いてかえでの口から流れてきた言葉は、普段と変わらぬ柔らかなもの。
だからこそ、すみれに有無を言わせない強さがあった。その上出鼻を挫かれれば、尚更。
「……はい」
相手のそんな強かさを恨めしく思いながら、すみれは大人しくそう返事をする。
するとかえでは笑みを浮かべたまま、目の前にあるチョコレートの残骸を手際よく片付け始めるのだった。
結局その後すみれがかえでに勝てる筈も無く、調理は滞り無く順調に進む。
やがて二人はそれぞれ、見事に幾つかのチョコレートを作り上げたのである。
* * *
躊躇する友人を半ば強引に付き合わせ、無理矢理チョコレートを完成させた次の日。
まだ二月であるといえ凍えてしまいそうな程の風に身を震わせながら、かえでは普段と同じ通学路を
ひとり歩いていた。
学校に近づくにつれ徐々に増えていく、同じデザインの制服。彼等一人一人の後ろ姿を確認しながらふと視線を
戻すと、いつの間にか彼女は最後の曲がり角まで辿り着いていたことに気付いた。
周りの流れに乗ってそこを曲がれば、路地裏から大通りに出る。
すると駅に近いこの路は普段から人通りが多い為、かえでの視界に入る後ろ姿も一気に倍以上に増えた。
何を話しているのか分からないが、甲高い笑い声を上げている女生徒達。彼女達のクラスメイトなのか、
その姿をどこかそわそわとしながら追いかける男子生徒。
しかしよく見れば彼等のような生徒は他にも居り、かえでは改めて今日という日の大きさを
思い知らされるのだった。
元々、商業主義に素直に甘んじることは好きではない。
昨日すみれが言っていた今日の本当の意味も、彼女は勿論知っている。
そしてその方が健全で、何より素敵だとも。
尤も貰うだけでは癪なので、お返しを贈ることも忘れないように。
かえでがそんなことを思いながら周りの流れに身を任せていると、妙に身体を密着させた男女がその視界を
通り過ぎる。ほんの少しだけその姿を追えば、自分達の世界に入っているらしい彼等は彼女のすぐ後ろで
口付けを交わした。
その瞬間にかえでは慌てて視線を戻し、自分のことでも無いのに熱くなってしまった頬を冷ます。
ペタペタと自らの頬を撫でていると、スピードの落ちた彼女を今度は彼等が追い抜いてゆく。
するとその目に、男子生徒の手に握られた小さな箱が映った。どうやら彼等の儀式はもう済んでしまったらしい。
そのテンションだからこその先程の行為である、とは限らないのだが。
それでも、ゆったりとしていたかえでの足取りが少しだけ軽くなる。
そして羞恥心から染まってしまった先程とは違う理由で頬を染め、にっこりと嬉しそうな笑みを浮かべた。
製菓会社の商業主義に、思いっきり便乗してやったのだ。これくらいの、いやこれの半分以下の恩恵くらい
期待してもいいではないか。せめてあの絹のように白い頬をほんのりと染め、ビスクドールのような美しい顔に
浮かんだ柔らかな微笑みを自らに向けてくれるくらい。
そんなことを考えていると、いつの間にかかえでの足は軽いスキップを踏んでいた。
目の前に広がる少しだけ浮わついた雑踏にもフィルターがかかり、まるで色とりどりの花たちに囲まれている
気分である。
だが校門をくぐろうとした彼女が思わず鼻歌を口ずさんでしまいそうになった時、慌てて唇を塞いだその目に
見慣れた金髪が映る。
いくら校則が緩いとはいえそんな派手な色の髪を楽しんでいる生徒は数える程しか居ない。
その上男子生徒よりも頭ひとつ分背が高い女生徒となれば、『彼女』以外に存在しないだろう。
先程から浮かれていたかえでは更に目を輝かせ、自らの手をどけ唇を解放する。
それと同時に、相手がこちらを振り返った。
しかしその視線はかえでの遥か先、正確に言えば相手のすぐ後ろ。
それもその筈、彼女はまだその名を呼んではいないのだ。
人混みに逆らうように、かえでの足が止まる。
視線の先には、苦笑を浮かべた『彼女』と、見たこともない女生徒。恐らく呼び止めたのは彼女だろう。
女生徒は暫くの間恥ずかしそうにもじもじとしていたのだが、やがて意を決したように顔を上げると、
綺麗に包装された箱を『彼女』に差し出した。
困ったような表情を浮かべたままの『彼女』は何事かを呟きながらも、結局はそれを受け取る。
その手には、学校指定の鞄の他に大きな紙袋がひとつ。勿論既に中身は入っているようだ。
羞恥心からか女生徒はすぐに走り去ってしまい、立ち止まったままのかえでの横をすり抜ける。
一方相手は箱を見つめた後で深々と溜息を吐き、それを無造作に紙袋へと押し込んだ。
そのまま振り返りもせず、ゆっくりと校舎の扉をくぐり視界から消えていく。
その後ろ姿を、かえではじっと見つめていた。
そして人混みの中にそれが完全に消えてしまっても尚、彼女は暫くその場に立ち竦んでいた。
ミルクのように白い肌、西洋人形のような美しい顔立ち、切れ長の目を彩る長い睫毛、冬の日に淡く輝く金色の髪
……そしてかえでが何よりも好きな、深緑の美しい瞳。
そんなマリアの微笑みを求めているのは、かえでだけでは無かったのである。
* * *
やがて時は流れ、流れるように動いていった太陽が低い頂点を通過した頃。
かえでは勉学の間のつかの間の休息を友人達と過ごしていた。
一人の弁当はとうの昔に空、ちびちびと食べていたもう一人のものもそうなりつつある。
しかしかえでの目の前にあるそれは未だ殆ど崩れてはいない。
それもその筈で、彼女は一口運ぶ度に深い溜息を吐き、何かを思案するように
ぼうっと天井を見上げているのだ。
そんなことをしていては、昼休み中に食べきることができるかも怪しい。
「かえでさん、食わないならアタイが食ってやるぜ?」
暫く何か言いたげに彼女の弁当を見つめていたカンナが、ついに耐えきれなくなったのかそう問いかける。
その口元からは今にも涎が垂れそうであることは言うまでもない。
「いいわよ……全部あげるわ」
いくら弁当を見つめていても食欲の沸かなかったかえでは、そう言って目の前の弁当を彼女の前に滑らせる。
元々自分で作ったものであるため罪悪感が有るわけでも無し、それならば美味しく食べてくれる相手に
あげた方が食材も本望というものだろう。
「ホントか? サンキュー!」
この上なく嬉しそうに礼を言って、カンナがかえでの弁当を掻き込み始める。
すると彼女の隣に座っていたすみれが眉間に皺を寄せた。
「ちょいとカンナさん! そんなはしたないことをなさる前に仰ることがあるでしょう?」
上流階級に育った彼女はこういったマナーに煩く、食べることさえできれば恰好など気にも留めないカンナを
よくこのように叱っている。だが今回ばかりは悪いことをしてしまったか、と二人を横目で見つめていたかえでは
心の中で呟いた。
シチュエーションが違うとはいえ、彼女が食べているのは自分の手作りのお弁当。
お手製の料理で何度もカンナを、そしてかえで達をもひっくり返してしまう腕の持ち主としては悔しいに違いない。
勿論、当の本人は自覚すらしていないのだろうが。
「んぁ、むぁんあお」
「飲み込んでからお話しなさい!」
口一杯に食べ物を詰め込んだ状態で口を開こうとしたカンナを、すみれはそう怒鳴り声を上げて制した。
そして急いで口を動かし始めた相手を見ながらフンと鼻を鳴らし、やがて視線をかえでの方へと向ける。
「……大丈夫ですの? 具合が悪いのなら、酷くならないうちに早退なされた方が宜しいかと」
まさか自分に彼女の視線が向けられるとは予想していなかったかえでは一瞬だけ目を丸くし、そしてその言葉に
納得する。高飛車で口が悪い印象のあるすみれだが、本当はただ素直になることができないだけであることを
かえではよく知っていた。だからこそ目の前の気を置けない友人である自分に食欲が無ければ心配するに
違いない。逆の立場であったらかえで自身もそうするだろう。
「大丈夫、ちょっと自分の思慮の足り無さに腹が立っているだけだから。それでお腹いっぱいなの。
でもありがとう、心配してくれて」
友人の心遣いに少しだけ心を溶かされたかえではそう言いながらにっこりと微笑む。
その言葉通り、単に気分を害していただけで体調が悪いわけではないのだ。
「んぐ、よく分かんねぇけど少しくらい喰っといた方がいいぜ?」
するとどうやら食べ物をのどの置くに追いやったらしいカンナが、すみれに続いてそうかえでを気遣う。
彼女は元々とても優しく、分け隔てなく気遣うことのできる人なのだ。一緒に居て安心できるその微笑に、
かえで自身何度助けられたことか。
「カンナ……ありが」
かえでが礼を述べようと口を開いた時、ふと相手の手元が動き目の前の弁当の中からまだ手を付けていない
卵焼きが姿を現す。そしてそれは言葉を発し終わっていないかえでの口元まで運ばれ、反射的に彼女はそれに
かぶり付いた。
「……っカンナさん!はしたないですわよ!!」
一瞬で頬を真っ赤に染めたすみれが再びそう怒鳴り散らす。かえでから見れば露骨に嫉妬しているようにしか
思えないのだが、それでも本人は無自覚なのだろう。
「別にいいじゃねえかよぉ、いちいちうるせぇなぁ」
流石に二度目ともなると黙ってはいられないのか苛立った様子でカンナはそう吐き捨てると、再び残った弁当を
掻き込み始めた。だがそれに相手が黙っていられる筈もなく、すみれの眉間に深い皺が刻まれる。
一触即発とはこのような状況をいうのだろう。尤も世間から見れば犬猿の仲である彼等にとっては日時茶飯事。
普段であればかえでも放っておくのであるが、今回ばかりは流石にその火種を蒔いたという負い目がある。
「まあまあまあ、落ち着いて二人とも。ほら、これあげるから」
すみれが口を開くよりも早にそう言ってく大袈裟に手を振ったかえでは、机の横に掛けてあった鞄から
小さな包みを2つ取り出した。
レースをあしらった透明な袋に入れられリボンで飾られたそれは、昨日作ったチョコレートである。
勿論『彼女』に宛てたものではない。
いっそ作るのであればと、家族や友人達の分も準備しておいたものである。
するとそれが目に映った途端、すみれの表情が硬直する。
「んぐっ!」
そして何故か、勢いよく弁当を食べていたカンナまでもが咳き込みはじめた。
「あらあら、あんまり掻き込むからよ」
いきなりの彼女の様子に驚きながらも、かえではそんなことを言いながらその大きな背中を叩く。
するとカンナは机上にあったお茶の蓋を開け、ぐびぐびと一気に飲み干してしまった。
「っぷは~悪ィ、いきなりだったんでちょっと驚いてよぉ……」
ようやく落ち着いたらしいカンナの言葉に、かえではああ、と小さく呟いてにっこりと微笑む。
失礼な話かもしれないが、彼女の生活では今日という日のイベントを知らなくても不思議ではない。
だからこそかえでは、共犯者にすみれを選んだのだから。
尤もひと悶着あった後になってみれば、そう代わり映えはしなかった可能性の方が高いのではあるが。
「ふふっ、今日はバレンタインだから。どうせなら思いっきり便乗しようと思って、昨日作ったのよ」
「ふぅん……ありがとな、かえでさん」
包みを手に取りまじまじと見つめていたカンナは、かえでの言葉に嬉しそうに微笑む。
全てを包み込むようなその表情に、彼女は暖かな気持ちになると同時に少しだけ切なさを覚えた。
ああ、この人が自分の本命ならば――
「どういたしまして……ほら、あなたも渡したら?」
脳裏に浮かんだ台詞をぐっと飲み込むと、かえではそう言って視線を滑らせる。
自分さえも暖かくしてしまったその微笑みを、今目を丸くしている彼女が見ずに誰が見ようというのか。
「えっ、なっ……何の事ですの?」
そのプライドの高さと羞恥心からとぼけるすみれの背中を、かえでは言葉という両手でぐいぐいと押す。
この手の話には奥手すぎる程奥手の彼女には、まるで力士の張り手のような力強い押しが必要だろうか。
「もう、そんなに恥ずかしがらないの。せっか上手くできたんだから」
彼女のとどめの言葉に、すみれは顔を真っ赤にして下を向く。
そして暫くの間前髪の間からチラチラとカンナとかえでを交互に見つめ、やがて観念したかのように
鞄の中を探りだした。
その手から無造作に放り出される、ひとつの小さな包み。
赤と青のチェック柄のリボンがそれに彩られている。
カンナによく似合う色だ、かえでは改めてそう感じた。
「おっ、おめぇにしてはちゃんとしてるじゃねぇか……どれどれ」
カンナは嬉しそうな表情を浮かべリボンをするりと抜き取ると、現れたチョコにそう言って目を見開く。
それは苺にチョコレートを絡め固めただけのシンプルなもの。
最初から有り得ない方法でチョコを溶かし始めたすみれを見た、かえでの苦肉の策である。
勿論、味は保証済。
「え、あの、今召し上がらなくて……も」
すみれには似合わないそんな弱気な言葉など耳に入る筈もなく、カンナはチョコに刺さったスティックを摘まみ
口に入れる。
既に味わっているかえではそんな彼女の表情よりも、じっとすみれの方を見つめていた。
「おお、美味ぇじゃねえか!ありがとな、すみれ」
カンナの感嘆の言葉と共に、彼女は一瞬だけかえでが見たことも無いような表情を浮かべる。
頬を染め、顔のパーツをくしゃくしゃにした、何よりも嬉しく、何よりも愛しいと感じているであろうそれに、
彼女もまた自然と口の端が緩んでしまった。
恋する乙女というものは、皆こんな顔をするのだろう、と。
「……な、と、当然ですわよわたくしが作ったのですから」
勿論それはほんの僅かのもの。次の瞬間すみれは普段とあまり変わらない表情を浮かべ、やがて照れ隠しの
高笑いが教室中に響き渡る。
そう簡単に素直な彼女は拝めない、ということだろう。次にそんな日がくるのはいつの日か。
「あ、あと五分しかねぇじゃねえか。マリアどこ行っちまったんだろうなぁ~」
すみれの表情をどこか満足げに見つめそんなことを考えていたかえでの耳に、何気ないカンナの言葉が響く。
だが同時にそれが聞こえたのだろうすみれは、すぐに高笑いを止め慌ててカンナの方に向き直る。
「ち、ちょいとカンナさん!」
「んぁ?」
すっかり目の前の食料を食べ尽くし物欲しそうに未だ中身が詰まったままの弁当箱を眺めていたカンナは、
すみれの声に目を丸くした。
そしてかえでは表情を一向に変えることなく、ゆっくりと視線をそれへと向ける。
包みがほどかれただけの弁当箱の持ち主は、箸を取り出す暇もなく女生徒から呼び出され姿を消していた。
またそれはこの時間だけの話ではない。
授業が終わる度『彼女』は毎度同じように呼び出され、始業ギリギリになり戻って来たかと思えば、
幾つかのチョコレートを抱えている。
そんなことを何度も繰り返され、かえではチョコレートを渡すどころかろくに話すこともできないでいた。
そしてそれこそが、かえでの食欲不振の原因であることは言うまでもない。
「……いいわよ、カンナ。食べちゃいなさい、マリアのお弁当」
暫くの間ぼうっと弁当箱を見つめたかえでは、やがてぽつりとそんなことを呟いた。
「えっ、でもいいのか?」
それは微かなものであったものの、こと食べ物に関してはかなりの地獄耳を発揮するカンナの耳には
届いたらしい。彼女の言葉は戸惑っているように思えるが、今にも涎を垂らしそうなその口元を晒してしまっては
台無しである。
「私が許すわ、勿体ないし。あの子に言われたら私のせいにしちゃいなさい」
「う~ん、じゃあ遠慮なく……」
そんなカンナにかえでが微笑みを浮かべそう促すと、笑みと戸惑いをごちゃ混ぜにした表情を浮かべた彼女は、
しかし素早く弁当箱を手に取った。やがてその蓋を開けて感嘆の言葉を漏らすと、ガツガツとかぶり付くように
中身を流し込んでゆく。気持ちよくなる程の食べっぷりとは、正にこのことをいうのだろう。
「……怒ってますのね、かえでさん」
深い溜息を吐いてカンナの様子を見つめていたすみれは、様子を伺うように呟く。
「別に、そんなことないわよ」
彼女の言葉にそう答えると、かえではすっかり空になった弁当箱もそのままにゆっくりと席を立った。
すみれの言葉は、当たっているようで外れ。結局かえで自身の中では、こうなることを予測できなかった自分に
腹は立てど、『彼女』に対しての感情はまた違うのだ。
そしてその正体は、彼女自身にも分からない。
かえでは教室を出ると、きょろきょろと廊下を見渡してみる。
だが普段ならばあれほど簡単に見つかるマリアの姿は、どれだけ目を凝らしても結局見つけることが
できなかった。
* * *
食後の眠気を伴う緩やかな時が流れ、気付けば夕刻。
部活帰りの生徒達に紛れながら、すみれは普段よりも遅いこの時間に帰路についた。
短い冬の夕暮れがもうすぐそこまで迫り、降り注ぐ日の光はもう大分淡い橙色になりつつある。
そうなればあっという間に落ちてしまうだろう。
すみれは下駄箱で靴を履き替え、外へと足を踏み出す前に一度後ろを振り返る。彼女の脳裏に浮かぶのは、
未だひとり教室に残っているのだろう、淋し気な笑顔の親友。
『もう少し待ってみるわ。だからあなたは、先に帰って』
彼女の想い人のあまりの仕打ちに一言言わなければ気が済まないと、すみれは暫く共に教室に残っていた。
帰宅部の生徒はひとりふたりと消えてゆき、気付けば部屋の中には二人だけ。
勿論文句を言いたい当人は、ホームルームが終わった途端にまた見知らぬ生徒に呼ばれて
消えてしまったまま。
その後一時間以上待ったものの、音沙汰は無し。
やがて教室どころか校内からも人の気配が少なくなった辺りで、親友はそう言ってすみれを先に
送り出したのである。
勿論、彼女は留まろうとした。
だがこれ以上自身が居残れば余計に相手を気遣わせてしまう。
そう考え、彼女は薄暗い部屋にひとりを残し教室を後にしたのだった。
冬の夜が長いこともあり早く帰るようにとは言ったものの、後ろ髪を引かれる思いであることに変わりはない。
だが呆然と待ちぼうけているわけにもいかず、すみれはゆっくりと自らの歩を進め始める。
「おう、すみれ」
そんな声が耳に飛び込み彼女が息を飲んだのは、校舎の扉から外へと足を踏み出した時であった。
「全く、こんな時間まで何してたんだよ」
所属している運動部のパーカーに身を包んだカンナは、そう言いながらすみれの前に立ち塞がる。
汗を滲ませていないことを考えると、既に部活の終了時刻から時間が経っているらしい。
「べ、別に何でもいいじゃありませんか」
強制的に足を止められたすみれは自らに向けられた真っ直ぐな瞳を見ることが出来ず、
そう言ってふっと目を反らせた。
自らの言葉は、普段とあまり変わらない。だがどうしても、いつものように相手の顔を睨み付けることができない。
何故ならすみれの脳裏には、自らが贈ったチョコレートを『美味い』と言って微笑んだその表情が
未だに残っている。
その上自らの中心の中には、沸き上がってしまった熱い気持ちがずっと燻り続けているのだから。
黙ったままのすみれの姿を見たカンナは、不思議そうに首を傾げる。
やがて大幅に鈍くなってしまったすみれの感覚がやっと背中に人の気配を感じた頃、その手がぎゅっと強く
握られた。
「……まあいいや、ちょっと来いよ」
目を見開いた彼女が口を開くよりも早く、カンナはその手を引いて外に出る。
「ち、ちょいとカンナさん……!?」
生徒の間を普段の彼女のスピードよりもゆっくりとした速度で走り抜ける相手にすみれは声を上げるものの、
本人からの返事はない。
しかしチラチラとこちらを振り返る素振りを見せていることを考えると、どうやら気遣う気持ちはあるようである。
一方すみれは、文句を言うこともできずただ黙ってカンナの後を追いかけていた。
勿論聞く耳を持って貰えないということもあるのだが、それ以上の理由がもうひとつ。
彼女の耳には、いや彼女の世界にはもう手を繋いでいる相手しか居なかったのである。
周りの喧騒は耳を塞ぎたくなる程の心音に掻き消され、熱に侵されているのか見慣れている筈の景色がまるで
違うもののように見える。
日常の中の非日常とは、こんな状況をいうのかもしれない。
だがそんな中でただひとつ、カンナの手の温もりだけがすみれの感覚の中で確かなものであった。
「……っと、ここなら大丈夫だろ」
まるで永遠のように思えた時間は、そんな声と共に唐突に打ち切られる。同時に離された手に不安を覚え
無意識にその温もりを追いかけたすみれは、ふと辺りを見渡して現実へと意識を取り戻した。
玄関から渡り廊下の下を潜った、校舎裏。昼休みには弁当を広げた生徒の憩いの場となり、また授業中には
自主休講を選んだ生徒の隠れ場となる。
そして人気の無い放課後には、恋人達が密かに愛を交わす場所であるとも噂されていた。
ごくり、とすみれは喉を鳴らす。
ゆっくりと辺りを見渡したものの、誰一人として見当たらない。
そして下校する生徒の喧騒など遥か彼方である。
「あ、あのカンナさ……」
「……ん」
自らの身体が熱くなっていくことに耐えきれなくなり、すみれがおずおずと声を出す。
だがそれと同時に、相手は言葉を遮るように何かを彼女の前に突き出した。
「えっ、な……」
「やるよ、お前に。内緒だぜ?」
状況が飲み込めず口をぱくぱくとさせるすみれに向かい、カンナにやりと悪戯っぽい笑みを浮かべる。
その表情に思わず目を反らすと、今度は視界にほんの少しだけよれた包装紙が映った。
その右上には、あの記念日を表すキラキラとしたシール。
嫌というほど思い知らされた、恋人達の日。
「いやぁ……アタイ、バレンタインは1人にしかチョコレートやっちゃいけねぇんだと思ってたんだ。
マリアもひとつしか作らねぇって言うし」
無意識に出していた自らの手の上に包みを乗せると、カンナは頭を掻きながらそんなことを話始める。
呆然としたままのすみれはその殆どを聞き流していたのだが、ふと見知った単語に目を見開く。
彼女に連れ去られるまで、ずっと頭の中を占拠していた親友の名前。そしてその相手の『彼女』に関する
意外な事実であった。
もしそうならば、その相手は……いやそうでない筈がない。
そう確信すると同時に、肩の荷が降りたのかすみれの身体がすっと軽くなる。
「でもかえでさんや色んな奴に貰っちまってホントびっくりしたぜ。これしか買ってなかったからよぉ……」
更に言葉を続けるカンナの瞳を、すみれはやっと真っ直ぐに見上げた。
彼女には青い空がよく似合う。瞳と同じ色だから。
彼女には真っ赤な色がよく似合う。
ハツラツとした性格とその暖かさは、皆を、そしてすみれ自身を包み込んでくれるから。
「……どうして、わたくしに?」
相手の言葉の間を縫い、すみれはゆっくりとした口調でそう問いかける。
するとカンナは一瞬目を見開いた後、ほんの少しだけ頬を染め、照れたような表情でこう答えた。
「マリアに、一番好きな奴にチョコレートあげる日だって聞いてよ……好きな奴って沢山居るけど、
何でか最初にお前の顔が浮かんだんだ」
相手の答えはすみれの欲しかったものそのものであり、また同時に全く違うものでもある。
だが彼女は心から沸き上がる気持ちに逆らうことなく、そのままの表情で口を開いた。
「……ありがとう、ございます」
「ん、いや、その……どういたしまして」
自らの表情を、すみれ自身が知ることはできない。
しかし照れくさそうに笑ったカンナを見た彼女はふと思った。
恐らく自分も、同じような表情をしているのだろう、と。
* * *
夕焼けはあっと言う間に闇へと堕ち、空の低い所で月が淡く光る。人気の少なくなった校舎にはぽつりぽつりと
明かりが灯り始めたものの、かえでがそのスイッチを押すことは無かった。
自らの姿さえ消えてしまう程、薄暗い教室。
昼間と全く同じ場所である筈なのだが、今はまるで異空間に迷いこんでしまったかのように
受ける印象は全く違う。
淋しく静まり返ったその空間は、やはりどこか不気味な雰囲気を漂わせていた。
世間のどこの学校でも七不思議が流行るのは、そんな理由からなのかもしれない。
しかしかえではそれに臆する様子も見せず、ただじっと夜空を眺めていた。
硝子一枚を隔てただけの外の世界には、冬の透き通った空気の向こうに美しい星空が広がっている。
彼女は結局渡すことのできなかったチョコレートの包みを机上で玩びながら、ただ呆然とその幻想的な光景を
見つめていた。
結局かえでが今日『彼女』と交わしたのは、簡単な挨拶と悪意をたっぷりと込めた仕返しのみ。
後者には特に相手からの言葉は無く、ただ溜め息混じりに苦笑されただけ。
だがその反応のお陰で、かえでは自らの感情が相手に全て読まれていたことを思い知らされたのだった。
沢山の好意に囲まれる『彼女』。その全てに嫉妬し、少しでも意識をこちらに向けたいが為に起こした悪戯。
冷静になって考えれば、好きな子に悪戯をする小学生と大して変わらない。
いや、そちらの方が純粋で可愛らしいといえるだろう。
嫉妬にまみれた黒い感情など、醜いことこの上ない。
ふぅ、とかえでは深い溜め息をひとつ吐いた。
そしてチョコレートを持ったまま、ゆっくりと椅子から立ち上がる。
そして半ば捨てるようにして、自らの席からふたつ後ろの机にそれを放り投げた。
カタン、という音が静かな部屋に響き渡る。
昼間ならば大したことのない其がまるで花火のように大きなもののように感じられ、かえでは思わず目を閉じる。
そして再び沈黙が降りたところで、彼女は再び瞼を上げた。
だが今度はまた別の大きな音が響き渡る。
「……よかった、まだ待っていて下さったんですね」
また目を閉じたかえでがそれをドアの音だと認識した時、その耳に飛び込んできたのは聞き慣れた、だがやけに
懐かしいと思える声。
瞬間、かえでの耳に自らの心音が大きく鳴り響く。
「……もう私のことなんて、忘れちゃってるんだとばかり思っていたけど」
そのあまりの大きさに思わず耳を塞ぎたくなるのだが、彼女はまるで何事も無かったかのように
冷静な言葉を返した。
勿論、視線は放り投げたチョコレートから外さないままで。
「まさか、私がどうしてあなたを忘れられるんですか?」
靴の音が徐々に近づいてくる。
それに比例するようにかえでの心音は早くなり、今にも破裂しそうな程に大きな音をたて始めた。
「それは、自分の胸に聞いてみなさい。私はもう帰るから」
耐えきれずに自らの胸の辺りを抑えながら彼女は言うと、机に掛けてあった鞄を取る。
そして相手の表情を見ないように下を向いたまま、早足でその場を去ろうとした。
「あ、待って下さい!」
彼女が正にその横を走り去ろうとした時、相手の声が教室じゅうに響き渡る。
するとかえでの体は、触れられてすらも居ないものの唐突にその動きを止められる。
そう意識すらしていないのだ。
彼女の愛するその柔らかな低い声を、振り切ることなどできる筈もない。
「何?」
「これ、ありがとうございます」
振り向き様に視線を移せば、相手の白い手が机上にあるチョコレートを手にしていた。
自らラッピングしていた為にどうしても素人の出来になってしまった上に、ずっと玩んでいたために少しだけ
よれている包み。かえでの目に、それは相手が貰ったのだろうチョコレートのどれよりもくすんで映る。
「……どういたしまして。でもそんなの、こんなに沢山のチョコレートに囲まれたら、すぐに埋もれてしまうわ」
苦笑を浮かべたかえでは、自らのチョコレートから逃げるように目を逸らす。
だが視線を少しだけ上げた時、それは相手の手によって持ち上げられ追いかけてくる。
彼女がその追跡を振り切るように視線を更に上げると、いつの間にかそれは遥かに高い位置にある筈の相手の
それと重なっていた。
透き通った、まるで宝石のようなグリーンの双貌。
かえでがその淡い光に射抜かれた時、その目が笑み形に歪む。
「そんなことはありませんよ。かえでさんのチョコレートは特別ですから、嬉しいです」
淡い月明かりに照らされたマリアは、そう言って嬉しそうに微笑む。
彼女の白い頬はその光にも負けず、ほんのりと桃色に染まっていた。
その姿がこの世のものと思うことができず、かえではごくりと喉を鳴らす。
それほどまでに今の彼女の姿は美しかった。
「……あなたは今日、もう何度そんな顔を見せたのかしらね」
そう独り言ちると、かえでは相手の表情につられるかのようにゆっくりとそちらの方へと近づいてゆく。
そして触れたいという欲求のままに両手で彼女の眼鏡を外すと、あっと言う間にその唇を奪った。
柔らかいその感触は、しかしかえでのそれよりも冷たい。
どうやら舞い上がっているのは自分だけであったようである
彼女はピンク色のその表面だけを軽く舐めた後、ゆっくりと唇を解放した。
すると目の前のマリアは、きょとんとした表情のまま自らを見下ろしている。
珍しい彼女の姿に、かえでは思えずふっと息を漏らした。
だが次の瞬間、彼女の背中が何か暖かいものに包まれる。
かえで自身がそれに気付いた頃には、既にマリアの両腕がしっかりとその腰を捕らえていた。
「……まさか、バレンタインにあなたまで頂けるとは思っていませんでした」
彼女は口元に優しいだけではない笑みを湛え、吐息混じりの声で囁く。
生温い感触にかえでかえでが思わず目を閉じると、ほぼ同時にその唇が塞がれた。
かぶり付くように触れた相手のそれはすぐに熱を誘い出し、絡め捕られた舌の感触に思わず彼女は
マリアにすがり付く。息を吐くことすらも許さない程の口付けは重なる度に深くなり、かえでの口からは幾度と無く
やるせない声が漏れる。
だが耐えようにも頼るものは何もなく、結局すがることができるのは相手の身体のみ。
しかし制服のリボンが絡み合う程に密着すれば、同じように口付けもより深さを増してゆく。
結局、かえでに逃れる術は無いのである。
「……っもう、駄目よ……ここでは」
唇の端から漏れた唾液が首筋まで流れ着いた時、かえではやっとの思いでそう声を発する。
繋がった銀糸に名残惜しさを感じるのは、彼女自身がそう思っているから。
荒々しく深いところまで、だが同時に繊細な刺激を与えてくる相手の唇は、こういうことに対してあまり積極的では
ないかえでさえもすぐにその気にさせてしまうのである。
それはマリアが『上手い』からなのか、それとも彼女自身が相手にそれほど惚れ込んでしまっているせいなのか。
もしくは、その両方なのかもしれない。
「誘ったのは、かえでさんでしょう?」
何時の間にやら片方の手をかえでの腰から胸の辺りまで移動させていたマリアは、カーディガンの上からそれを
なぞりつつ呟き、にっと唇の端を曲げる。何枚もの布地のせいで肌には何も感じられない筈なのだが、
その手つきの艶めかしさにかえでは思わず息を飲んだ。
「ぐっ、し、仕方ないじゃない。だって」
「したかった、から?」
ふふふっ、とマリアは笑いながら彼女の言葉を遮る。
かえではその言葉の意味をどう捉えていのか分からず、相手の顔を不機嫌そうに見つめたままでで口を噤んだ。
確かに彼女の姿に見惚れたのは事実。
それに触れたいと感じて手を伸ばすと、邪魔だと思った眼鏡を外しその唇に口付けた。
あの時の彼女が強く願ったのは、そこまでの筈である。
だが彼女の感情は――欲望に塗れたそれは、果たして本当にそこまでで満足したのだろうか。
今この瞬間に自らを解放したマリアの腕を、こんなにも欲しているというのに。
「これでは、私のプレゼントだけでは足りそうにありませんね」
マリアはそう言って彼女から離れ、机の脇に掛けられた鞄からひとつの包みを取り出す。
どうやら、彼女が準備したものも手作りであるらしい。
「今日はこれひとつしか持ってきませんでしたから」
ふわりとした柔らかい素材に包まれたそれを、彼女はかえでの手を取り握らせる。
よく見れば結ばれたリボンの辺りに、流暢な筆記体でその名が描かれていた。
「……ありがとう。ホワイトデーでもよかったのに、みんなと一緒で」
溶けてしまいそうな程の温かい気持ちに包まれたのもつかの間、ほぼ同時にかえでの心には切なさが過る。
マリアの姿からほんの少しだけ視線を外せば、今日一日思い悩んだ元凶が嫌でも目に映るのだ。
運よく自身が一番に貰うことができたものの、優しい彼女はきっと全てにお返しをするのだろう。
ご丁寧なことにその為の日も、企業は準備しているのだから。
だが、そんなことを考え熱の冷めてきたかえでの耳に返ってきたのは、予想外の相手の言葉と、
同じく予想外の相手の表情であった。
「みんな、とは?」
不思議そうに首を傾げ、マリアはそう問いかける。
少々意地の悪いところはあるとはいえ、かえで自身の口からそれを言わせようとするほど彼女は残酷ではない。
そうなれば本当に分かっていないということか。
「私は知らないわよ。あなたのファンはこんなに沢山居るんだもの」
だが故意ではないと分かりながらもかえでは口に出すことができず、その代わりに視線をそちらへと移した。
マリアの机の横には大きな紙袋、その中には大量の贈り物の数々。
クラス中の男子生徒でも、ここまで集めた輩は居まい。
「……かえでさん」
ふう、と深い溜息を吐いたのと同時に、自らの名を呼ぶ声が降ってくる。
その声のトーンが呟いた本人が苛立っている時のものだと気付いたかえでは、驚きと共に反射的に声の主を
見上げた。
「これは、私が今年のバレンタインに贈る最初で最後のプレゼントです」
プレゼントを持ったままの手を強く引かれ思わず目を閉じた彼女の耳に、力強いマリアの声が響いた。
最初で、最後の。
とても信じることのできないその言葉を反芻しながら、かえでは驚きに目を見開く。
そこにはどこか不機嫌な様子のマリアが居り、やがてそれはゆっくりと彼女の方へと近付いてきた。
「どれだけ頂いたとしても、私がチョコレートを贈るのはあなたひとりですよ……かえでさん」
他は全部、返せないと釘を刺しましたから――吐息のかかるほどの距離でそう囁くと、
マリアは目を見開いたままのかえでにまた口付ける。
甘いだけではない乱暴なそれは、淫猥な水音を教室中に響かせた。
低いところに出た月が、淡いながらも明るく闇を照らし始めた頃。
誰も居ない教室ですっかり身体の力が抜けてしまったかえでに、マリアはこう囁くのだった。
「すみません。あまりにも、お腹がすいてしまったもので」
* * *
春の立つ日が過ぎたといっても未だ冬の寒さが辺りに満ちているような、そんな季節の朝。
同じ制服の学生たちが行き交う道で、四人は偶然顔を合わせた。
違う方向からばったりと出会う形になったカンナとすみれは、顔を合わせるのと同時にもはやスキンシップとも
いえる言い合いを始め、そんな彼らに合流したマリアとかえでは、顔を見合わせふっと笑う。
そしてかたや言葉を、かたやお互いの指を絡ませたまま、再びゆっくりと流れに乗って歩き出した。
門を潜れば、またいつもと同じ日々が始まる。
だがそれぞれが経験したあの日は確実に、その日常にまた新たな色を乗せていた。
決して誰も見ることなどできない、『赤い糸』という名の色を――
+++++++++++++++
……誰か作って下さい!!!(切実)
PR
ご案内
こちらは、わとことくらゆきの二人が運営する「サクラ大戦」の帝都ごった煮二次創作サイトです。
全体的に女性キャラ同士が非常に仲の良い描写が含まれること、更に製作物によってはキャラが崩壊していることがございますので、観覧の際はご注意下さるようお願い致します。
その上最近はCPが節操無し状態になっておりますので、より一層ご注意願います。
初めていらっしゃった方は、必ず「あばうと」のページをご覧下さい。
尚、このサイトは個人で運営しているものであって、版権物の著作者様・販売会社様等とは一切関係ありません。
サイト内の文章・イラスト(バナー除く)の無断転載・転用はご遠慮下さい。
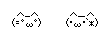
全体的に女性キャラ同士が非常に仲の良い描写が含まれること、更に製作物によってはキャラが崩壊していることがございますので、観覧の際はご注意下さるようお願い致します。
その上最近はCPが節操無し状態になっておりますので、より一層ご注意願います。
初めていらっしゃった方は、必ず「あばうと」のページをご覧下さい。
尚、このサイトは個人で運営しているものであって、版権物の著作者様・販売会社様等とは一切関係ありません。
サイト内の文章・イラスト(バナー除く)の無断転載・転用はご遠慮下さい。
カレンダー
| 10 | 2025/11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
カテゴリー
最新記事
リンク
リンクフリーに甘えています。
ごめんなさい。
帝撃 りんく倶楽部 様
冷えトロ 様
復活草 様
Closet Land 様
夢のつづき 様
Karo-Tosen 様
同じ太陽の下で 様
さくら咲いた 様
はしゃぐな危険 様
風の鳴る木 様
銀刀満月 様
カキチラス 様
犬小屋 様
ごめんなさい。
帝撃 りんく倶楽部 様
冷えトロ 様
復活草 様
Closet Land 様
夢のつづき 様
Karo-Tosen 様
同じ太陽の下で 様
さくら咲いた 様
はしゃぐな危険 様
風の鳴る木 様
銀刀満月 様
カキチラス 様
犬小屋 様
プロフィール
HN:
わとこ , くらゆき
性別:
非公開
自己紹介:
詳しくは「あばうと」のページを御覧下さい。
ブログ内検索
